マノン・レスコー どんな作品?
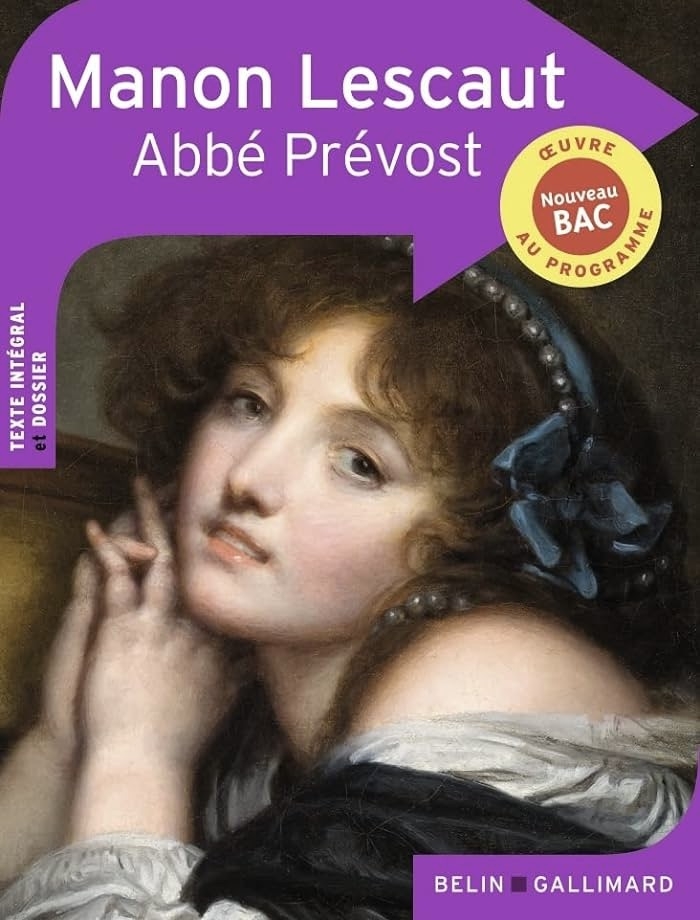
・作品内容
音楽性と情熱に溢れ、悪徳と美徳の永遠の衝突を軸にしたロマンティックな物語。二人の若者の一目惚れの恋(幾多の困難の中で花開く)で幕を開け、海外の砂漠の荒廃の中で悲劇的に幕を閉じる苦い物語。
官能性に満ちたこのオペラは、イタリア語を「語り」ながら、音楽的には国境を越えた経験、とりわけワーグナー、さらにはスクリャービンやデ・ファリャにも目を向けている。
絶対的な主人公は18歳の少女マノン・レスコー。彼女の生みの親であるフランスの作家アントワーヌ・フランソワ・プレヴォストと同じように)悪の化身であり、無意識かつ無責任で、その魅力は彼女に近づく者を破滅へと導く。
第1幕:18世紀のフランス。学生デ・グリューは、弟のレスコーとともに田舎からアミアンへやってきて、修道院のあるパリへ向かうマノンと恋に落ちる。金持ちの老ジェロンテはマノンの美しさに心を奪われ、彼女を誘拐しようと企む。しかし、マノンはデ・グリューと共にパリへ逃げる。
第2幕:マノンがジェロンテが提供する裕福な生活を好むようになる様子が描かれる。しかし、デ・グリューが彼女に追いつくと、情熱が再燃する。ジェロンテは復讐のためにマノンを糾弾し、窃盗と売春の罪で逮捕させる。
第3幕:マノンは投獄され、アメリカへ流刑される準備が整う。マノンの婚約者と兄が彼女を解放しようと試みるが徒労に終わる。しかし、デ・グリューは恋人の後を追って、キャビンボーイとして乗船する。
第4幕:二人の若者は再び逃亡者となり、アメリカの荒野にいる。マノンは疲れ果て、最愛の人の腕の中で息を引き取る。
・作曲家について
ジャコモ・プッチーニ(1858~1924)は、ヴェルディの後継者であり、19世紀末の後期ロマン派の精神だけでなく、20世紀初頭の新しい刺激性をも語る術を知っていたトスカーナの作曲家である。言葉では言い表せないほど美しいメロディーを奏でることができるプッチーニは、大衆の好みの変化や新しい流行にも常に気を配り、作曲の方法を常に新しくしようとした。好奇心旺盛で、具体的で、独創的な彼は、オペラの舞台となる国とその時代の音楽文化を研究した。
「マノン・レスコー」はプッチーニの3作目のオペラであり、彼の最初の真の傑作である。1893年2月1日、トリノのテアトロ・レージョでこのタイトルが鮮烈なデビューを飾ったとき、このトスカーナ出身の作曲家は35歳だった。その数日後(2月9日)、ミラノ・スカラ座でジュゼッペ・ヴェルディ最後のオペラ『ファルスタッフ』が上演された。これは偶然の一致であると同時に、ヴェルディの時代であった19世紀の幕引きと、プッチーニという次の世代を担う天才の叙階という意味において象徴的なバトンタッチでもあった。ルッカ出身の作曲家でありながら、世紀末のヴェリズモ的な音楽的衝動を部分的にしか受け入れず、独自のスタイルを創り上げた(それは、後に『ラ・ボエーム』、『トスカ』、『蝶々夫人』、『トゥーランドット』といった彼の他の傑作に見られることになる)。
彼は音楽を通して、若く情熱的で軽薄なマノンの複雑な感受性、多面的な個性を語り、私たちを魅了することに成功した。
プッチーニは女性を深く愛し、女性のために最も美しいメロディーを書く。彼のオペラに登場するヒロインは皆、大きな衝動を経験し、大きな愛を生きる。そして、彼女たちはほとんどいつも悲劇的な結末を迎える。ちょうど『マノン・レスコー』の最終幕で起こるように。3幕までにほとんど全てのメロディーが現れ、最終幕においては、主人公の過去の感情を思い出させ、彼らの最後のドラマにさらに感情移入させる「メモリーの音楽」である。
・誰がマノンを "創作"したか
「"ボヴァリー夫人"が史上最高の小説であるように、これは史上最高の短編小説である。」ある作家は、1728年から1731年にかけて書かれたプレヴォスト大修道院長(1697-1763)の物語『Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut』をそう評した。
夢中にさせる、当時としてはスキャンダラスな物語で、おそらく実体験に由来するものだろう。実際、プレヴォストの伝記的な出来事と、主人公デ・グリューの出来事には明らかな共通点がある。宗教的な召命と人生を全うしたいという願望の間で葛藤し、スキャンダルに巻き込まれ、最後には教会に引き戻される(作者は聖職者となり、修道院長として生涯を終えた)。
この物語は出版された直後、検閲によって発禁処分を受けた。その結果、人気は高まった。社会通念に反抗し、感情に身を任せた二人の若者の物語は、すでにロマン主義に親しまれてきた雰囲気やテーマを予感させながら、後戻りできない地点で文学に炸裂した。
さらに、物語のリズムの速さ、独特の心理描写の巧みさ、舞台のリアリズムなど、この作品には明らかに現代的な要素が含まれている。この作品は大成功を収め、プレヴォストは死の直前に新版を編集した。
1765年、『マノン』の物語は戯曲となった。そして、この物語の影響は18世紀をはるかに超えて広がった。
・悪女の「母」
プレヴォストは『マノン』によって、18世紀初頭の小説における貞操の模範とはまったく異なる、曖昧なヒロインの世代を築いた。彼女に続く女性の文学的登場人物の中には、デュマ・ソンの『カメリアの乙女』の主人公マルグリット・ゴーティエをはじめ、プロスペル・メリメの『カルメン』、フランク・ヴェデキントの『ルル』などがある。いずれも致命的に魅力的な女性で、決して悪質ではないが、恋人たちに社会的・道徳的破滅をもたらす。
プレヴォストの傑作と『椿姫』(ひいては後者を下敷きにしたヴェルディの『椿姫』)との関連は、デュマ自身によって明確に明かされている...。アルマン(主人公)は、物語の劇的な場面で、愛するマルグリットがテーブルの上に残した本を発見する...。愛するシュヴァリエ、あなたは私の心の偶像であり、私があなたと同じように愛することができるのは、この世界にはあなたしかいない。
しかし、金欠の恐怖は彼女にひとときの安らぎも与えなかった。彼女には余暇と娯楽が必要だった。お金をかけずに楽しむことができるのなら、彼女は一銭も手を出さなかっただろう。しかし、娯楽は彼女にとってなくてはならないものであり、娯楽がなければ彼女の気分も意思もあてにならなかった。
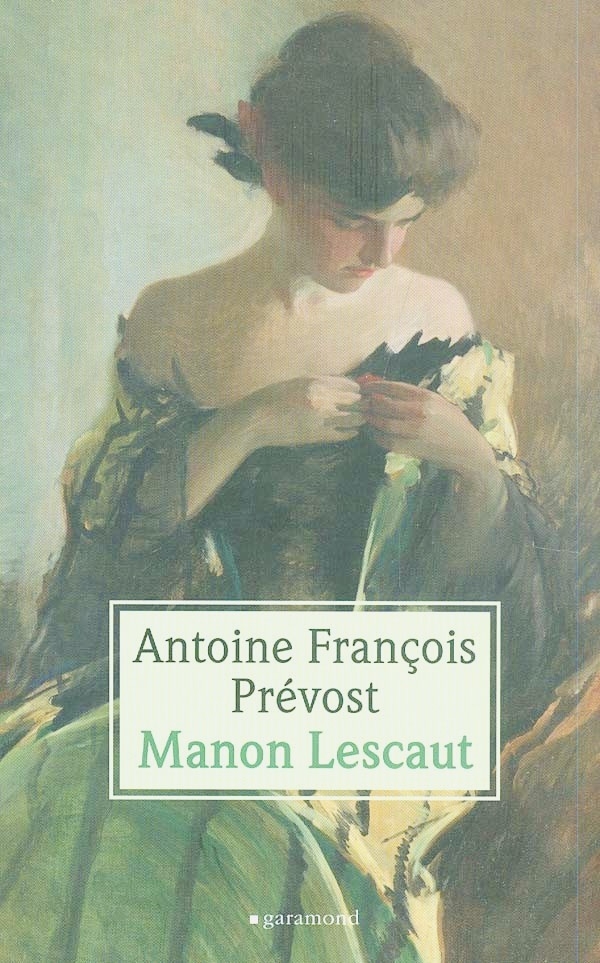
・いくつのマノンがオペラ化された?
プッチーニがプレヴォストの18世紀の題材を音楽化するという選択は勇気あるものだった。1887年に上演されたサルドゥーの「トスカ」を音楽化する権利を得るために奮闘したが徒労に終わり、プッチーニは「マノン」に狙いを定めた。
既に、1856年、ダニエル・オーベール(ウジェーヌ・スクライブの台本によるオペラ・コミック)、そして1884年、ジュール・マスネ(アンリ・メイラクとフィリップ・ジブリの台本)の作品が存在した。
MeihlacとPhilippe Gilleの台本による後者の作品はヨーロッパの主要な劇場で大成功を収めた。プッチーニの友人たちや出版社のリコルディ自身はこの作品に反対したが、トスカーナの作曲家の返事はこうだった:「マスネはフランス人として、マノンを火薬とメヌエットで感じた。私はイタリア人としてマノンを絶望的な情熱を持って感じるのだ!」
・オペラのリブレットはほぼ協同作業
今回のプッチーニの「マノン・レスコー」のリブレットには、台本作家のサインがない。それは「父親」がいないからではなく、むしろ「父親」が多すぎるからである!
音楽化される詩のテキストは、マスネが使用したものとは異なるオリジナルなものにしたいという願望から、同僚や文学者の間を転々とする。劇作家(スカピリアトゥーラの流れを汲む)マルコ・プラガ、出版社ジュリオ・リコルディ、作曲家ルッジェーロ・レオンカヴァッロ(作曲家と劇作家の間で、いまだその天職に迷っている)、文筆家ドメニコ・オリーヴァ、ジュゼッペ・ジャコーザ、ルイジ・イリカ...。そしてプッチーニ自身である。
オリヴァが詩にした当初のプラガの企画は、マスネのフランスの台本作家が扱ったストーリーに近いものだった。しかし、プッチーニ自身の圧力により、すぐに大幅な変更が加えられた。
イタリア語版では、デ・グリューの父親の登場はなく、さらに、青年は修道院長にはならない。
マスネはル・アーヴルで物語を止め、プッチーニは付録のような(アメリカ的)第4幕を提案した。

